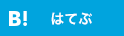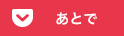ライター安次嶺隆幸

「負けたい自分」と上手に付き合う。勝ち負けを決めるのは自分自身【子供たちは将棋から何を学ぶのか】
ライター: 安次嶺隆幸 更新: 2017年06月28日
最後の最後で「負けました」と頭を下げて対局が終わるのをご覧になった方もいらっしゃることでしょう。勝ち負けを最終的に決めるのは、対局者自身なのです。勝負であるのにもかかわらず、判定をする審判がいません。自己責任の世界がそこにはあるのです。
審判がいない自己責任の世界
一般の勝負の世界では、第三者の目で見て、勝敗を決める審判が存在します。将棋にも近くにいて対局を見ている人はいますが、それは記録係や立会人です。審判の役目を務めるのは 対局する両者です。将棋は両者の信頼関係で成り立っていて、勝ち負けはこの二人に任されているのです。
プロに限らずアマチュアの対局も、誰も見ていないことだってあります。誰も見ていないのをいいことに、負けた方が勝手に「俺が勝った」などと言いだしたら、おおごとになってしまいます。でもそんなことにはならず、負けた方が自ら「負けました」と宣言して勝負が終わる。何のトラブルもなく一人は勝ち、もう一人は敗れたとお互いが認識する。そして、投了後にはお互いの健闘をたたえ、さらなる棋力向上のため、感想戦を行います。
このように当事者である対局者を信頼し、勝敗の判定が任されているというところに日本文化の奥深さを感じます。

(第61期王座戦 第1局より )
常に最善の一手を選択し続けることが逆転につながる
将棋は、「詰み」になって勝負が決まります。「詰み」を端的に言えば、自分の王様に王手をかけられて、それをどうやっても解消できないという状態です。
初心者の場合は一目瞭然の詰みとなったところで、「負けました」ということが多いので分かりやすいです。しかし、上級者になって、先の先まで読めるようになってくると、模様が悪いことまで読めてしまいます。まだ詰みではなく、土壇場ではないけれど、先の先まで読むとこれでは自分は詰みになってしまっているのではないかという時があるのです。
極端に言えば、先の先まで、例えば50手先まで読んで負けが見えてしまった時にどうするか。ここで「負けました」と言ってしまうこともありうるわけです。
しかし実際には、こちらが選んだように相手が指すとは限りません。 自分が「詰まされている」と思っても、あくまでそれは自分の読みであって、相手の読みではありません。相手がこちらの読みのように指さないことも十分あり得るわけです。
将棋はお互い一手ずつしか指せません。その一手一手の積み重ねで、必ず100点の手を指し続けられるかと言ったら、そうとは限りません。
仮に自分が80点の手を指したとします。相手が100点の手を指してきたらいくらやっても追いつきません。しかし、相手の手が81点であれば、わずか1点に縮まるのです。差をつけられて苦しいと思っていても、相手が急にマイナス50点の手を指してしまうということもあるのです。
負けていると思ったにもかかわらず、堪え忍んでとにかく最善を尽くしているうちに逆転して勝つこともあります。だから将棋は面白いのです。
「負けたい心理」に負けない強い心で
逆転の可能性が残されているのですから、どんな場合でも我慢して、最善を尽くして戦い続けなければなりません。相手が強いから、50手先を読んだら負けているから、とひるむのは、勝負を捨てて逃げてしまうことになります。
相手を過大評価したり自分を卑下したりしてはいけないのです。これは将棋に限らず何事にも言えることだと思います。
河合隼雄先生の心理学の本に「人間の心理には、負けたい心理がある」ということが書いてあって、なるほどと思いました。
「負けたい自分」と「勝ちたい自分」がいる、と。でもついつい「負けたい自分」が出てしまう。なぜなら、苦しくなったとき、「負けたい自分」を出せばラクだから。
負けたらもう先を読まなくてもいいし、苦しまなくていい。 それに、早い段階で「負けました」と宣言したら、いかにも潔さそうで、ある意味かっこいいように見えます。そんな「負けたい心理」に、負けてしまってはいけません。
かといって「勝ちたい自分」を前面に出しすぎても、焦り・気のはやりにつながります。それも自分に負けてしまうことです。
「負けたい自分」と上手に付き合いながら、「勝ちたい自分」も抑えなければいけない。そして、ここが勝負だ、ここは我慢してじっくり考えるときだという局面では、ぐっと踏ん張って勝負する。それが大事なのです。

(第61期王座戦 第2局より )
自分との戦い、究極の自己責任を体現する
踏ん張りどころで考え抜き、考えうる最善の手を指さないことには、せっかく勝ちを目前にしていても局面がガラッと変わってしまい、次は自分がピンチを迎えることになります。将棋は、いかに考え抜けるか、という自分との戦い、究極の自己責任の勝負なのです。自分に克てたかどうかは、自分自身が一番よくわかるはず。審判が存在しないのも、それゆえのことなのかもしれません。
子供たちは将棋から何を学ぶのか