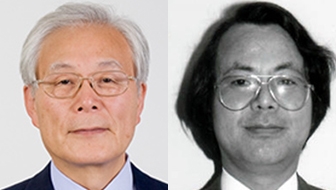ライター一瀬浩司
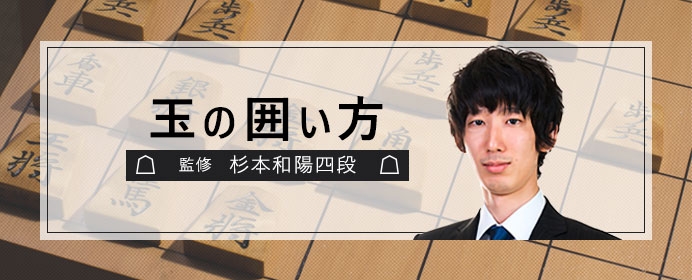
非常に簡単な囲い、三手囲いの注意点と発展形【玉の囲い方 第66回】
ライター: 一瀬浩司 更新: 2019年05月09日
前回のコラムでは、振り飛車における「三手囲い」をご紹介しました。今回は、組む際の注意点と発展形を見ていきましょう。それでは、三手囲いに組むまでの手順の復習です。初手から▲7六歩、▲6六歩、▲6八銀、▲5八飛、▲4八玉、▲3八玉、▲4八銀(第1図)。
【第1図は▲4八銀まで】
それでは、組む際の注意点を見ていきましょう、と言いたいところですが、見ての通り、非常に簡単な囲いです。よって注意すべき点はあまりありません。しいて言うならば、相振り飛車には適していないということでしょうか。第2図をご覧ください。
【第2図は△2五歩まで】
相振り飛車で三手囲いに組んだ一例ですが、2筋が非常に薄いですよね。こうなると、銀は3九のままのほうが、いつでも▲2八銀と2筋を強化できますのでまさっています。第2図から▲3六歩としても、△2六歩から飛車先を交換されて3七に銀を上がる手が間に合っていませんね。
というわけで、三手囲いは相手が居飛車のときのみに採用することにしましょう。では、次に囲いの発展形を見ていきましょう。
囲いの発展形:第1図から、▲2八玉、▲3八金(第3図)とすれば、「金美濃」になります。
【第3図は▲3八金まで】
3八の駒が銀ではなく、金のため金美濃と言われています。こうなると、玉が深く2八まで囲われ、堅さも増していること見るからにはっきりと分かりますね。さらに、第3図から、▲1六歩、▲4六歩、▲3六歩、▲4七銀、▲3七桂(第4図)と進めると「木村美濃」になります。
【第4図は▲3七桂まで】
木村美濃とは、木村義雄十四世名人が香落ち上手を持ったときに愛用して連戦連勝したため、この名がつけられたようです。現在ではプロ同士の駒落ち戦はまったく見ることはできませんが、当時は八段相手にも香落ち戦を指すことがあり、そのことだけでも木村十四世名人がいかに強かったのかがわかりますね。
現代では、香落ち戦は奨励会二段以下まででしか指されることはなくなりましたが、プロの香落ち戦を見てみたい、という方も多いのではないでしょうか? 数年前に将棋世界の企画で、トップ棋士対若手棋士で香落ちから始まる二番勝負(上手が勝ったら角落ち、下手が勝てば平手)が行われたことがありましたが、確か上手の2勝4敗だったと記憶しています。また、第1図から、▲4六歩、▲4七銀、▲3六歩、▲3七桂、▲4八金(第5図)と進めると?
【第5図は▲4八金まで】
どこかで見た形ではありませんか? そうです、以前ご紹介しました、右玉の形になりますね。
このように、三手囲いは簡素な陣形ですが、そこからさまざまな形に発展させていくこともできます。
玉の囲い方


監修杉本和陽四段
1991年生まれ、東京都大田区出身。2017年4月に四段。師匠は(故)米長邦雄永世棋聖。バスケットボールを趣味とする。ゴキゲン中飛車を得意戦法とする振り飛車党。