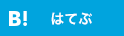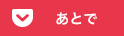ライター安次嶺隆幸

相手との関係の中で決断するということ【将棋と教育】
ライター: 安次嶺隆幸 更新: 2017年10月06日
我慢したり相手にゆだねたり曖昧さを残す「間接的な手」。危ないようでも、攻めに出る「直接的な手」。この2つの指し方のうち、どちらか一方しか使わないとしたら、将棋で勝つことは難しいでしょう。勝つためには、局面に応じて判断し、両方の指し方を組み合わせて使う必要があります。
その選択は、日常のコミュニケーションにも通じているのです。
相手とのコミュニケーションの中で手を決めていく
今年度の藤井聡太四段の快進撃を観て、その強さはなんだろうと多くの人が考えたはずです。私も棋譜を並べてみて思ったことなのですが、一直線の勝ちを目指して勝利をしているというよりも、相手の指し手から、どうも直接的な手か間接的な手かを考えて指し手を決めているように感じたのです。実際はその局面、局面での最善手を探して、指し手を決めていると思われますが、どうもそう思えてなりません。
実際は、直接的な手の方がいいか、間接的な手の方がいいか、100%の正解はありません。状況に応じて、どちらを指す場面かを見極めることが大切なのです。

将棋は、目の前の相手と一手ずつ、交互に指し手を進めていきます。直接的な手と間接的な手の緩急のつけ方、どこで勝負に出るかというタイミングは、相手との関係の中で見出していきます。決断のための材料を集め、一手を指すためには、人間力が問われます。観察力や洞察力、決断力、責任力など、トータルな人間力が、勝敗の行方を決める要因になるのです。
こうすれば絶対将棋が強くなれるという将棋上達の方程式は無いとよく言われます。それはひとつには、上達するにつれて、そのレベルに応じた上達法があることが原因だと思われます。
もうひとつの大きな理由として、上達の方法論はそれぞれ個々人の経験則にゆだねられていて、それを客観的に整理してまとめるのは難しいということが挙げられます。つまり、それぞれが実体験の中で自分なりの方法を獲得していくしかないのです。
要するに将棋の強さというのも、個々人の人間としての力と、相手にどう対応していくかというコミュニケーション力につながっているわけです。
日常のコミュニケーションでの直接的、間接的なやり取り

直接的な手と間接的な手。それをどう選ぶかは、そのまま日常のコミュニケーションに相通じます。
たとえば学級経営を例にとると、低学年の教室で落ち着きのない児童がいたような場合、その子に注意をするという直接的な方法と、その子の隣の姿勢のいい子を褒めるという間接的な方法があります。
私の場合は、後者を選択します。「きみは姿勢がいいね。先生は感心したよ。嬉しいな」などと褒めると、隣の落ち着きのない子もハッと姿勢を正し、こちらを向きます。そのとき、すかさず「さすが〇〇くん。きみもいい姿勢ができるじゃないか」と褒めてあげる。長年の経験から、直接叱るよりも効果的なことが多いです。
日常生活においても、例えば依頼を断るとき、「できません」「無理です」と直接的に言うこともできます。しかしそれでは相手のメンツをつぶすことにもなりかねません。大抵の場合は、相手を配慮して、「安請け合いしてかえってご迷惑をおかけしてはいけませんから、今回は遠慮させていただきます」などと、やんわりと間接的な言い回しを心がけるのではないでしょうか。
ただ、「考えさせてください」という婉曲な表現では、相手の受け取り方によっては、期待を抱かせてしまう場合もあります。状況によっては、あえてストレートに返事をすることもあるはずです。
相手との関係性や、現在の状況を考慮して、直接的な言い方と間接的な言い方を使いこなしていく。それは、まさに人間関係の機微にふれるものです。画一的なマニュアルなど作れるものではなく、それぞれが人間関係を見つめる中で自分なりの方法を見出していくしかないものでしょう。
将棋の指し手を選ぶときも、まさにそれと同じです。直接的な手と間接的な手をどう選ぶのか、自分なりの方法を見出していくしかないのです。
コミュニケーション力を育む、感想戦の文化に触れて

逆に言うと、子供たちはそうした兼ね合いを将棋の対局で学んでいく中で、知らず知らずのうちに人間関係の機微をも身につけているのです。
低学年の子供たちが対局後に感想戦をしているのを見ると、本当にその思いを強くします。初めのうちは結果にこだわり、悔しいとか恥ずかしいとかがどうしても先に来てしまいます。しかしそのうち、「きみ、こうだったね」「ああ、そうか。じゃあこうすればよかったんだ」などというやりとりをするようになるのです。
そうした会話を聞くにつけ、子供たちの成長ぶりに目を見張り、頼もしく感じます。
感想戦を含めた将棋の構造そのものが、成長のプロセスになっているのではないでしょうか。
子供たちは将棋から何を学ぶのか