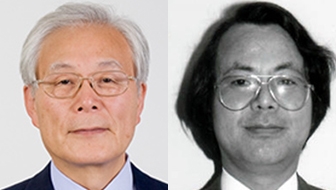ライター高野秀行六段

四間飛車を指すなら必ず覚えるべき「3つのセオリー」居飛車の急戦に対応しよう【はじめての戦法入門-第3回】
ライター: 高野秀行六段 更新: 2016年11月25日
皆さん、こんにちは。棋士の高野秀行です。さて今回はいよいよ本格的な戦いとなります。まずは四間飛車を指すには絶対に覚えなければいけない「対急戦策」についてです。前回最後に出てきたキーワード「捌(さば)き」も出てきます。まずは第1図をご覧ください。
第1図は▲1六歩と突き、「美濃囲い」が完成した局面です。これは前回の第2図と同じ局面。囲い方を復習してみてください。
【第1図は▲1六歩まで】
「美濃囲い」が完成しました。(前回コラム参照)
ここが後手の作戦の分岐点となります。△3三角と上がり、さらに玉を囲うのが「持久戦策」となります。これは次回に解説します。急戦では、居飛車が積極的に攻めてきます。
第1図から△1四歩▲5六歩△6四銀▲6七銀△7五歩(第2図)
【第2図は△7五歩まで】
△7五歩で駒がぶつかりましたこの攻めの第一歩を「仕掛け」といいます。
居飛車が△1四歩から△6四銀と出て来ました。この動きに対して▲5六歩~▲6七銀とします。この▲6七銀は後手の攻めに備えたとても大切な一手。居飛車の銀が四段目(自分から見て)に出てきたら、絶対に指してください。
△7五歩と駒がぶつかりました。居飛車が攻めを「仕掛け」てきた局面で、今回のポイントとなる一手があります。
第2図から▲7八飛(第3図)△7五歩を▲同歩と取ってはいけません。△同銀▲7六歩に△8六歩が厳しい攻めで、▲7五歩△8七歩成▲9五角△9四歩(参考1図)で角の行き場所がなくなってしまいます。先に銀は取れますが、これは振り飛車側の失敗です。
【第3図は▲7八飛まで】
「仕掛けの筋に飛車を動かす」絶対的なセオリーです。
【参考1図は△9四歩まで】
9五角が助かりません。居飛車の「銀を五段目に出させない」ことが重要です。
ここで今回最初のセオリーです。
「銀を五段目に出させない」
絶対に守ってください。そして、もう一つのセオリーが。
「仕掛けの筋に飛車を動かす」
これが最も重要なポイントとなります。今回は7筋なので▲7八飛と動かしました。なぜポイントなのか、続く手順で分かります。
第3図から△7六歩▲同銀△7二飛▲6五歩△7七角成▲同飛△5三銀(第4図)
【第4図は△5三銀まで】
▲6五歩から、まずは角交換。
△7六歩~△7二飛と攻めて来ました。この銀取りを▲6七銀と引いては△7五銀(参考2図)と「銀を五段目」に出られてしまいます。次に△7六歩が厳しい押さえ込みです。
【参考2図は△7五銀まで】
次に△7六歩と押さえ込まれると息苦しくなります。「銀を五段目にださない」ここでも大事です。
そこで登場するのが▲6五歩です。△7六飛は▲2二角成△同銀▲7六飛の切り返しがあります。これは飛車と銀の交換で駒得となり、振り飛車の必勝形です。
この▲6五歩を指すために▲7八飛と「仕掛けの筋に飛車を動かした」のです。△7七角成から角交換となり第4図。ここで「捌き」の登場です。
第4図から▲6七銀△7七飛成▲同桂△7九飛▲7一飛△9九飛成▲8五桂(第5図)
【第5図は▲8五桂まで】
>
「角交換から飛車交換」。桂が自然に前に進み百点満点の「捌き」となりました。
▲6七銀と引くのが好手です。
「角交換から飛車交換」
これが大事なセオリーです。
△7七飛成から△7九飛と攻めて来ましたが、▲7一飛から▲8五桂と跳ねます。次に▲6六角や▲8一飛成と指したい手があり、振り飛車優勢です。
大駒を交換し、左の桂が自然に進む手順を「捌き」といいます。「捌き」は感覚的な言葉で、説明するのは難しいですが、この手順のように駒の損得がなく、左の桂が前に進めば「捌けた」と思って良いでしょう。
また第5図でもう一つ注目してもらいたいところがあります。それは「玉の囲い」です。
先手と後手、どちらが堅そうに見えますか? どちらも守りの陣地に「玉」がありますが、先手の美濃囲いのほうが、金銀が連携していて、玉も2筋にいるので、後手よりも安全です。では、今回のポイントは以下のとおりです。
居飛車側の急戦策に対しては
- 「銀を五段目に出させない」
- 「仕掛けの筋に飛車を動かす」
- 「角交換から飛車交換」
実戦で試して、「捌き」の感覚を身につけましょう! 次回は、持久戦に対しての指し方を解説します。
はじめての戦法入門