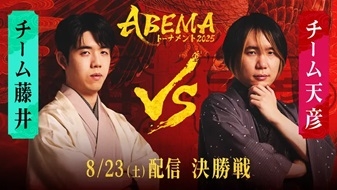ライター渡辺明

「固さからバランスへ、そして読みの重視へ」渡辺明二冠が平成で印象に残る羽生善治九段・藤井聡太七段との将棋を振り返る
ライター: 渡辺明 更新: 2019年04月28日
私が将棋を覚えたのは平成2年頃。将棋界の年譜を見ると平成4年頃からプロの将棋を観戦していたように思う。私は平成12年に棋士になったのだが、それ以前の出来事で印象深いのは、もちろん羽生善治九段による七冠制覇である。テレビや新聞での報道を見ていて全冠制覇がとんでもないことなのは小学生だった自分にも理解できた。
私が初めてタイトル戦に出たのは平成15年。そういった意味では私にとって「平成の将棋界」とは、前半は見ていたもの、後半は参加したもの、となる。このコラムは「平成で印象に残る将棋」という趣旨なのだが、自分が出たタイトル戦の中では何と言っても互いに永世竜王を懸けた平成20年の第21期竜王戦七番勝負である。その中でも特に内容が濃かった将棋を紹介したい。
第21期竜王戦七番勝負第1局はフランス・パリで行われた。駒袋から駒を出す渡辺竜王(当時)。
フランス・パリで行われた第1局。図1では穴熊+駒得で優勢を疑わなかったが、ここで手が止まった。結局のところ先手の攻めが成功している訳ではなかったようで、チャンスも作れずに負けた。AIの影響により現在では右玉の評価が高まっているが、平成20年当時はそうではなかった。穴熊が固さなら右玉はバランスの将棋でこの頃は固い玉形のほうが重視されていたが、現在は評価が逆転している。羽生九段の将棋を他の棋士が形容する時に「バランスがいい」は良く使われるフレーズだが、この将棋は現代のバランス感覚を10年先取りしたような内容だったと言えるのではないだろうか。
【図1は△6四角まで】
この竜王戦七番勝負はどちらも永世竜王が懸かるということで注目を集めたが、内容的にも第1局、第4局、第7局は反響が大きい将棋だった。1つのシリーズでこれだけ色々なことがあるのは相当に珍しいことで、周囲の期待が高まるにつれて集中力が研ぎ澄まされたことと、出だしに3連敗したことで開き直って指せたのがいい結果につながったのだと思う。
この局面では渡辺竜王は優勢を疑わなかったが・・・。
つい最近火災に見舞われたノートルダム寺院。その悲報は世界を駆け巡った。対局の2日前に観光で訪れた時の一枚。寺院の礼拝堂にて。
もう1局は今年2月に行われた藤井聡太七段との第12回朝日杯将棋オープン戦決勝戦。図2から▲3六飛△7五銀となって先手が勝てない将棋になった。▲3六飛に代えて▲7五銀と打てば先手有望だったというのが局後の藤井七段の指摘。加えて図の1手前の△3四歩では△7五銀と先着すべきだった、という感想もあった。これらの手は私には全く浮かんでいなかったので「1分将棋でこんなに読んでいるのか」と驚かされた。
【図2は△3四歩まで】

第12回朝日杯将棋オープン戦決勝戦で藤井聡太七段と対戦する渡辺棋王(当時)。
穴熊のように玉が固い将棋では攻めが多少は失敗しても悪くならないだけに読みの精度は問われないこともある。それに比べて現在、主流となっているバランスを重視する将棋は玉が薄いので1手のミスが命取りになる。すなわち、以前よりも読みの力が求められる時代になっているのだが、小学生の頃から詰将棋チャンピオンになるなど驚異的な読みの力を持つ藤井七段の活躍は将棋戦術の変遷を象徴する出来事だったように思う。
固さからバランスへ、そして読みの重視へ。将棋の戦い方が変わる中で元号が新しくなる。私は「平成」ではプロ棋士としての約20年を過ごした。新元号となる「令和」でもあの時の将棋は良かったなとしみじみ振り返れるようないい棋譜を残したい。
撮影:常盤秀樹