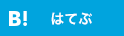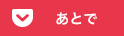ライター遠藤結万

「神話は終わったのか」第31期竜王戦第七局観戦記
ライター: 遠藤結万 更新: 2019年01月10日
一年間準備しても、防衛することすら難しいタイトルをことごとく防衛し、最後の一つを制覇して七冠となった棋士がいる。
一つ獲得すれば、時代を築いた棋士として永久に記憶される永世位を、七つ獲得した棋士がいる。
多くの棋士が、一生に一度でも獲得したいと熱望し、それでも取ることが出来ないタイトルを、九十九期も獲得した棋士がいる。
彼は、誰もが不可能だと思うことを達成し続け、やがて神話となった。

対局前に駒を並べる羽生(左)と広瀬(右)
第31期竜王戦第七局、二日目。どちらの棋士が勝っても、将棋界にとって歴史的なタイトルマッチになることは、よくわかっていた。対局の地である山口県下関市には、東京から新幹線で小倉に向かい、門司港から下関までフェリーで向かう。長い旅路だ。それでも、見届けなければならないと感じていた。
北九州市と下関はたった五分のフェリーで結ばれている。フェリーから降りて10分ほど歩くと、対局場のある「春帆楼」に着く。眼の前には関門海峡が広がる。ふぐ料理を食べたいところだが、モバイル中継を読むと、そんな余裕はなさそうだった。
すぐにメディア控室に向かう。中継モニターの前には、和服を着た険しい顔の二人の棋士が座っている。右には、羽生善治竜王(いずれも肩書は当時)。神話となった棋士、その人が前かがみになり、深い読みを入れている。
盤を挟んで相対しているのが、広瀬章人八段。王位のタイトル獲得経験があり、今はA級に所属している。今最も乗っている棋士の一人と言ってもいいだろう。
「100期か無冠か」ばかりがフィーチャーされているが、この竜王戦は「神話的な棋士・羽生善治」に「最強の挑戦者・広瀬章人」が挑むタイトル戦でもあるのだ。
広瀬は今31歳、まさに「指し盛り」である。前回タイトルを獲得したのは23歳。まだ大学生の時だった。「王子」と呼ばれたその時とは、使っている戦法も、積んできた経験も、全く違う。
彼の将棋歴は、不思議と羽生と縁がある。広瀬が生まれたのは、1986年の1月、つまり羽生がデビューした年度である。羽生はこの年、勝率一位を記録した。広瀬が奨励会に入った1998年、羽生は二十八歳と伸び盛りの時期であり、四つのタイトルを保持していた。
もっとも、これはアンフェアな言い方だろう。羽生は長い間、常に三冠、四冠を保持し続けたのだ。どの時代のどんな年度を切り取っても、そこには羽生がいるのだから。
広瀬はもともと実力が高い上、今期は絶好調と言っていい。一組で堂々の優勝を果たし、久保・深浦と言った強豪を破ってこの七番勝負に進出した。
そして、羽生は今期、スランプとまでは言わないまでも、勝率は往年ほどに高いわけではない。
常識的に考えれば、このタイトル戦は最初から、広瀬有利なはず。しかし、二日目に到着した時の控室には、羽生が防衛するのではないか、という根拠のない確信があった。
まるで、おとぎ話が必ず「めでたし、めでたし」で終わるのと同じように。
時代は常に移り変わる。かつて三冠、四冠を保持するのが当たり前だった時代から、ジリジリと二冠、そして棋聖を失冠して「竜王」となっても、多くの将棋ファンは最強棋士だった羽生の残像を追いかけていた。
2日目、封じ手の時点では、形勢は少し羽生が指しやすいと見られていた。

封じ手の様子
【70手目 △7三金で広瀬八段が71手目を封じる】
広瀬の飛車は玉の近くにおいやられた。そんな控室のムードが変わったのは、午後四時頃だった。117手目、▲3五銀。広瀬の馬が羽生玉を睨む。馬のラインが容易には止まらない。
【117手目 ▲3五銀】
メディアの雰囲気が張り詰める。竜王が容易ではない。いや、むしろ......挑戦者が良いのではないか。
控室は重苦しい雰囲気に包まれる。誰もが見たくないものを見るように、中継を見ていた。
ジリジリとした展開が続く。少しずつ土俵際に押し出されるように、羽生の手が伸びなくなる。盤上をぼんやりと見つめ、また天を見上げ、脇息に持たれる。そんな時間が長くなる。
検討室を覗くと、藤井猛九段、そして佐藤康光九段が、無言で中継を見つめていた。
佐藤も、藤井も、「羽生世代」と呼ばれ、羽生と切磋琢磨して戦ってきた実力者たちだ。しかし、タイトルを独占していたはずの羽生世代も、一人、また一人とタイトルを失い、いつしか羽生は、ただ一人のタイトルホルダーになっていた。

中継を見つめる佐藤九段
日が落ちるとともに局面は広瀬優勢から、広瀬勝勢へと変わっていた。それも、間違いづらい局面に。
将棋における「有利」は二つある。一度でも間違えればすぐにひっくり返る有利さと、何回か間違えても逆転しない有利さ。本局における広瀬の優位は、後者だった。
「逆転することはないでしょう」
「(席に戻ってきたら)投げるな」
控室には、そんな声が飛ぶ。もう決まっているなら早く投げろ、という雰囲気すら漂っていた。
気の早い棋士なら、いや、最近の羽生なら、形作りをして投了、となっていてもおかしくない。そんな局面が、一時間以上も続いた。投了するだろう、と準備していた記者の顔には明らかな疲労が漂っていた。
しかし、羽生は投げなかった。そしてもちろん、広瀬も間違えなかった。
何度も頭を抱え、うつむき、うめいた。羽生は指し続けた。まるで、突然若い頃に戻ったかのように、粘り続けた。
どんなときも泰然としている羽生の姿はそこにはなかった。鬼気迫るように、羽生は指し続けた。まるで、この将棋が終わると同時に、自分の寿命が尽きるのだ、と言うかのように。

劣勢になっても粘り続けた羽生
ある女流棋士は、終局後にこう言った。
「二十七年ぶりに無冠になる羽生さんの気持ちは、私には全く想像ができない」
タイトルを取ったことがある女流プロでもそうなのだから、私などにその気持ちが想像つくはずがない。
取材陣の顔には、眼の前で起きていることがまるで現実ではないように、まだなにかあるのではないか、という期待が浮かんでいた。
思えば、羽生善治という人は、常に「まさか不可能だろう」とでも言うような、周りの期待に応え続けてきた人だった。
前人未到の七冠。常に将棋界のトップランナーだった。まさかの失冠を繰り返した去年も、竜王位を獲得し、不可能に見えた永世七冠も成し遂げた。だから、皆が羽生の勝利には、単なる将棋の一局以上のものを求めるようになった。
局後、広瀬は「これからの人生で、これほど注目されることは、二度とないかもしれない」と語った。プレッシャーはあった、しかし、盤上では最善手を求めてきた、と。
広瀬は、神話に飲み込まれなかった。潰れそうな重圧に負けず、不利な局面でも諦めず、勝利の糸を手繰り寄せた。
広瀬はこうも語った。「羽生さんからタイトルを奪取しないと、一人前と見られないという視線があった」と。
不本意な形で羽生との対戦を取り上げられたこともあった。振り飛車も辞め、根本的に将棋を変えた。しかし、タイトルに手が届かない中でも、一歩一歩進んできた結果、竜王戦に手が届いた。
広瀬にも背負うものがあった。結婚し、家庭を持った。北海道で熱心に応援するファンもいた。いつまでも羽生に負け続けるわけにはいかなかった。
▲7二金。広瀬が非情な手を繰り出す。この手で虎の子の飛車が捕まった。羽生はがっくりと脇息に身体をもたれさせた。

頭を抱える両対局者
【151手目 ▲7二金】
「投了すれば終わりますので、記者の皆さんは感想戦の取材をお願いします」
連盟の職員が、記者に説明する。注目局だけに、将棋関連ではない記者も多数おり、現場は雑然としていた。将棋を知らない記者から「もう終わるの?」という声も聞こえるが、答えるものはない。
羽生は焦点の合わない視線を盤上に向ける。十秒、二十秒、少しずつ、羽生の寿命が縮んでいく。羽生がまた一度、うめく。身体を折りながら、力なく扇子を仰ぐ。
羽生は飛車を差し出し、涙がでるような粘りの手を指す。
数手進み、広瀬は少し震えるように、羽生の守りの銀の前に歩を打つ。この手で受けは完全になくなっていた。もう、これ以上、この将棋を指すことは出来ないのだ。
羽生は形を作り、首を差し出す。誰かが「詰んだな」とつぶやく。記者たちも慌てて準備に入る。羽生玉には、難しくはない詰みが生じていた。
「負けました」
▲2一銀の王手が指されると、すぐに羽生が投了を告げた。消え入りそうな声だった。
【167手目 ▲2一銀まで羽生竜王が投了】
慌ただしく報道陣が対局室に向かう。囲み取材が始まり、新竜王に質問が飛ぶ中、羽生はずっと顔を落としてうずくまっていた。
一瞬、羽生はこのまま命を落とすのではないか、と思った。それほど、顔は土気色で、生気が感じられなかった。しかし、それ以上に、勝者であるはずの広瀬の声も、小さかった。消え入りそうな声で、淡々と勝因を述べた。
「良いところと悪いところが出たシリーズだった」と広瀬は語った。まだ自分が竜王である、という実感がないように見えた。
羽生の取材が始まる。たくさんのシャッター音が響く。そのキャリアの中で、常に向けられてきたカメラ。しかし、今日だけは少し、意味合いが違っていた。 「自分の実力が足りなかった」と羽生は語った。
実力不足。その言葉が頂点を極めた人間から出ることは、他の業界では考えにくいだろう。
いったい、どこまで走り続けなくてはいけないのか。どんな実績があっても常に実力を高めなくてはいけない、そんな世界で羽生善治も、広瀬章人も、ずっと戦ってきたのだ。
気がつけば、立会人の藤井九段が静かに目を閉じていた。まるで静かに瞑想するように。その胸中に浮かぶものは、私にはうかがい知れなかった。

対局後にインタビューを受ける羽生
囲み取材が終わり、控室で田村康介七段が「ついにこの日が来てしまったね」とつぶやく。実感のこもった言葉だった。いつか羽生が無冠になることは誰もがわかっていたが、不思議なことに、そんな日が来ると誰も信じていなかったのだ。
メディアは争うように「羽生敗れる」の報を流し、終局後は「羽生無冠」あるいは「百期ならず」の言葉が踊った。
しかし、それは違う、と私は対局場の二人を見ながら思った。二人の棋士が戦い、一人が勝つ。将棋とは、結局のところ、それだけのゲームでしかない。
百期だ七冠だというのは、後付のストーリーだ。そして、神話は、神話でしかないのだ。
局後、広瀬はまだ実感がないながらも、嬉しさを隠しきれない顔で会見を行った。連敗した後の第三局、第四局の逆転勝ちが大きかった、と語る。時代はこれから切り開かれていくのだ。広瀬の晴れ晴れとした顔を見ながら、私はそう実感していた。

どこか重苦しい気持ちで、小倉への帰路につこうとする中、誰かの声が聞こえた。
「羽生さんは、どうせまた(タイトル戦に)出てきますよ」
その言葉で、少しだけ気持ちが軽くなった気がした。
羽生にとっても、広瀬にとっても、これは決して終着点ではない。羽生が切り開いた道も、広瀬がこれから切り開く道も、決してまだどこにもたどりついてなどいない。
広瀬新竜王も、羽生九段も、これからも更に素晴らしい将棋を見せてくれるはずだ。
広瀬はこれからますます成績を伸ばすだろう。羽生は順位戦で好調で、昨年惜しくも敗退した、名人への挑戦も可能な位置にいる。何も終わってなどいないのだ。
だから、今はただ、激戦となった第31期竜王戦における、勝者の栄誉と、敗者の健闘を讃えたい。
※写真は竜王戦中継ブログより