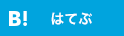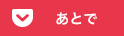ライター前田祐司九段

前田九段の〝お目を拝借〞第8手「アマ・プロ戦リターンズ」
ライター: 前田祐司九段 更新: 2019年12月05日
『週刊将棋』は今から3年前、平成28年(2016年)3月、将棋界での一定の役目を終え、休刊になりました。
その創刊は昭和59年(1984年)の1月でしたが、今回はそれから2年後、昭和61年の話です。
これまでにない速報性で、号を追うごとに週刊将棋は評価が高まっていました。時代にマッチしたのでしょうね。それはけっこうなことでしたが、編集部はさらなる躍進を目指し、目玉企画を立ち上げたのです。それは、「アマ・プロ戦」。
まだまだこの時代は、「プロは勝って当たり前。素人に負けるのは大いなる恥」という価値観が支配していました。それゆえ、勝負は世間の注目を浴び、ファンは結果が気になる――つまり、多くの読者が週刊将棋を購入する→売り上げが伸びる、という構図なんです。
こうした概念はマーケティングの一般論としてはすでに定番化もとおり過ぎ、当時でも陳腐な切り口でした。しかし、〝勝負〞というのはいつの時代も注目を集めるようで、また、速報性のある媒体特性から、結果と内容を早く知りたいというファンの気持ちをつかみ、企画は編集部の計算どおりの展開になったのです。
『将棋世界』にも「アマ・プロ平手戦」
実はこの企画の9年前、昭和52年に日本将棋連盟の機関誌『将棋世界』が「アマ・プロ平手戦」を企画し、翌年の1月号から1年間、月1局、掲載したことがありました。たぶん、定例的なアマ・プロ平手戦は、それが初めてだったと思います。
結果は、プロ側(全員、四段)が12戦全勝で終了。しかし、その後、第2弾が実施され、今度は(四段の)プロ側が指し分けという結果になったのです。そこで、将棋世界の編集部は第3弾の企画を立て、プロ側に五段の出場を要請してきました。私はその時、アマ・プロ戦に初めて出場したのですが、当初は頑(かたく)なに出場を辞退していたのです。
アマの快進撃
さて、週刊将棋の「アマ・プロ戦」ですが、これも手合いは当然「平手」です。
対局方式はたぶん、プロ側は四段から対局し、もしアマが勝ったら次局は五段、アマが負けたら選手を交代し、プロ四段と対戦するという"決め"だったかな?
しかし、週刊将棋が最初に送り込んできた刺客、それはとんでもないモンスターだったのです。その人の名は、小林庸俊(つねとし)さん。当時はまだ千葉大学の学生でしたが、学生名人を2度も獲得し、しかも、現役の朝日アマ名人でもあった超強豪です。
小林さんは、7月に初戦の中田功四段(当時C級2組。現八段)と対戦し、中田四段が得意とする振り飛車を撃破。快調なスタートを切ります。

当時の『週刊将棋』の記事1
続く8月、第2戦は富岡英作五段(当時C級1組。現八段)の矢倉を粉砕。これでファンは大いに盛り上がり、企画は編集部の目論見が大当たりになりました。
プロ側は驚くとともに、9年前、将棋世界誌のアマ・プロ戦が苦い思い出となって蘇ってきたのです。その中でもただ一人、さらに苦虫を噛み潰したような顔をしていたプロがいました。誰あろう、前田祐司七段です。

当時の『週刊将棋』の記事2
第3戦の六段戦は少し時間が空いて、11月になりました。プロは島朗六段(当時B級2組。現九段)。ここで当然、島さんが止めるとプロ側は思っていたのですが、ヒネリ飛車でまさかの敗退。
となるとですヨ、六の次は「七」が物事の道理。前田七段のイヤな予感は現実となったのでした。
六段戦翌日より、編集部から私への対局依頼の電話が押し売りのように何回も掛かってきました。
編集部:「前田先生、対局料6万円で七段戦への出場をお願いします」
前田:「お断りします!」
この時期、私はNHK杯戦ではツキが味方し、ベスト8に進もうかという快進撃を続けていましたが、2期目となる第45期順位戦B級1組は、不本意ながら降級争いの真っ最中だったのです。順位も下位から4番目の11位、成績は4勝5敗。首筋は凍りついていました。前期、A級の事情から3名がB級1組に降級してきたため、今期は定員が14名と一人多く、降級は3名。降級すれば即、ン百万円の減収です。週刊将棋の戯言(たわごと)に付き合っている暇は1秒もありません。
しかし、なおも電話は鳴り続け、「編集部です」・「お断りします」の遣り取りが無限ループやメビウスの輪のように続きました。今なら着信拒否設定ができますが、当時、電話機にその機能はなく、電話線を引っこ抜きたい心境でした。
でもなぜ、私なのか? 当時のB級1組・七段は、私のほかに真部一男、福崎文吾、田丸昇の各氏だけ。あとは八段か九段。で、真部さんは棋界のプリンスですから、万一の傷は付けられません。福崎さんは当時、「十段」のタイトル保持者。権威があります。田丸さんは前田より先輩。恥をかかせるわけにはいきません。その点、前田だったらナンでもアリ。それがストーカー電話の理由なのです。
電話はしつこく掛かり続け、最後は、「10万円!! 10万円!!」という絶叫で終わりました(私の粘り勝ち)。
代わりに田丸さんが出てくれましたが、小林旋風は止まらず、昭和62年1月10日、七段も敗退。私が出場していても、やはり負けていたでしょうネ~。小林さんの内容は皆、素晴らしかったですから。
これで、次はA級八段と対戦となったのですが、南芳一八段(現九段)がやっと旋風を止めてくれました。でも、もし負けていたら......?
敵に後ろを見せる私の臆病な性格が奏功。B級1組もナンとか残留できました。
前田九段の〝お目を拝借〞